
スポンサーリンク
尾高長七郎とは
尾高長七郎(おだか-ちょうしちろう)は、幕末の天保9年(1838年)に、武蔵国榛沢(はんざ)郡下手計(しもてばか)村(埼玉県深谷市手計)の尾高勝五郎の次男として生まれました。
母は尾高やへ(渋沢宗助の次女)で、兄に尾高惇忠(尾高新五郎)、妹に尾高ちよ、弟に尾高平九郎がいます。
兄・尾高惇忠は長男として家業を切り盛りしなくてはならなかったため、弟の尾高長七郎は、早くから江戸に出て、海保漁村(かいほぎょそん)から儒学を学びました。
また、伊庭軍兵衛(伊庭秀業)からは剣術(心形刀流)の指南を受けました。
スポンサーリンク
また、長州藩の久坂玄瑞、出羽の清川八郎、水戸藩の原市之進、宇都宮藩の河野顕三などの志士とも交流しています。
大橋訥庵の思誠塾にも入っていたことから、1862年、江戸では老中・安藤信正の襲撃謀議(坂下門外の変)の計画に参加しました。
その後、尾高長七郎は江戸に向かいましたが、安藤信正襲撃は、事前に露見し、身柄が拘束されると言う噂を耳にした渋沢栄一が、熊谷宿まで追いかけています。
そして、話を聞いた尾高長七郎は、信州を経由して京都へ逃れて尊皇攘夷活動の為潜伏しました。
文久3年(1863年)には京から深谷に戻っています
このように江戸や京都にて情報に接していたことから、世の中の情勢に明るく、渋沢栄一や兄・尾高惇忠が、高崎城の乗っ取り計画を企てると、難しいと説得して断念させました。
のち、渋沢栄一は「長七郎が自分ら大勢の命を救ってくれたといってもよい」と述べています。
翌年の1864年、中村三平・福田滋助と江戸へ向かう途中、戸田ヶ原(埼玉県戸田市)にて、誤って通行人を殺傷しました。
約5年間、伝馬町の獄にて過ごした結果、体を悪くしたようです。
新政府軍が江戸に迫る明治元年(1868年)4月9日、江戸城が開城する直前に赦免されて出獄し、深谷に戻ると療養しましたが、1868年11月18日に亡くなりました。享年31。
スポンサーリンク
この頃、渋沢栄一はフランスに出張中で、帰国後、尾高長七郎の死を知り、墓碑を建立しています。
2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」では、尾高長七郎を俳優の満島真之介さんが演じられます。
・尾高惇忠(尾高新五郎) 富岡製糸場の初代場長
・尾高千代 (渋沢千代) とは 渋沢栄一の最初の正妻
・渋沢宗助の解説 東の家の当主 渋沢まさ も
・渋沢栄一とは 日本の実業界・社会福祉・教育などに大きく貢献
・渋沢成一郎(渋沢喜作)とは 彰義隊・振武軍のリーダー
・尾高平九郎(渋沢平九郎)とは 渋沢栄一の養子になった飯能合戦の勇士
・真田範之助の解説【八王子出身の剣豪】天然理心流と北辰一刀流の志士
・平岡円四郎 一橋家の家老で慶喜の側近
・大橋訥庵(おおはしとつあん)の解説~坂下門外の変を画策した攘夷派の儒学者
・尾高やへ【簡単解説】
・高崎城とは? 群馬県高崎市の城跡
・青天を衝け キャスト・出演者一覧リスト【NHK2021年大河ドラマ】
スポンサーリンク
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
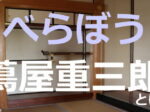
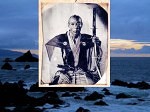


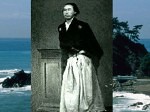




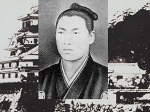
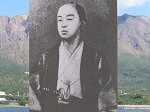

この記事へのコメントはありません。